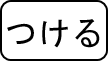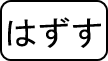大原小学校いじめ防止基本方針
大原小学校いじめ防止基本方針
1 いじめの定義
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 【いじめ防止対策推進法第1章第2条 定義】
2 いじめの禁止
いじめは、重大な人権侵害であり、決して許されない行為である。すべての児童はいじめを行ってはならない。また、児童はいじめを発見した場合、もしくはいじめの疑いを認めた場合はいじめを傍観せず、保護者・教職員または関係機関等に報告するよう日常的に指導を行う。
3 いじめ防止への基本的な考え方
いじめは、どの集団にも、どの学校にも、どの子どもにも起こり得るという認識の下、その防止に当たっては、特定の子どもや特定の立場の人だけの問題とせず、広く社会全体で真剣に取り組む必要がある。子どもの健全育成を図り、いじめのない子ども社会を実現するために、学校・保護者・地域など、大人がそれぞれの役割を自覚し、主体的かつ相互的に協力し、活動することが必要である。また、子どもが自ら安心して豊かに生活できる社会や集団を築く推進者であることを自覚し、いじめを許さない子ども社会の実現に努めていけるよう指導をしていく。
4 学校におけるいじめ防止の具体的取組
(1) 組織的な対応
ア 「いじめ対策委員会」の設置
いじめを始めとする子どもたちの問題行動は複雑化・潜在化し、教師一人での対応は難しい状況となっている。そのため、いじめの早期発見・早期対応・重大事態への対処を組織的に行うことによって子どもを守り抜くために、「いじめ対策委員会」を設置する。委員会の常設委員は校長・副校長・主幹教諭・生活指導主任・特別支援コーディネーター(養護教諭)・当該児童学年主任・担任とし、場合によってはSC・校区教育協働委員会・関係諸機関にも協力を仰ぐこととする。
イ 関係諸機関との連携
いじめの発見・又は疑いのあるケースが発見された場合には、直ちに校内での対応を進めるとともに、指導主事・「HEARTS」等関係諸機関と情報交換を行い、より良い解決に向けた取組を進めていく。
(2) 段階に応じた取組
ア いじめの未然防止
・「いじめは絶対に許されない」という意識を学校全体に醸成する。
・市民科学習等を通じて、人権を尊重する心情を育て、いじめをしない・させない・見逃さない資質・能力を育てる。
・学校と保護者ならびに保護者同士の緊密な連携・協力を推進するため、HPや保護者会、面談、学校だより等で、学校がいじめの未然防止に努める姿勢を示し、信頼関係を築く。
イ いじめの早期発見
・学級の様子と早期のいじめの実態把握を行うために、年3回の全校生活アンケート、4・5年生におけるハイパーQUアンケートを実施する。
・児童がいじめを訴えやすいよう、校内での相談体制を整備し、保健室や相談室の利用ができることを周知する。
・目安箱・まもるっち等を有効活用して、児童が直接相談できる窓口について周知する。併せて、相談シートを全校児童に配布する。
・SOSの出し方に関する教育についてのDVDを活用し、または参考にした授業を各学級1単位以上教育活動に位置付ける。
ウ いじめの早期対応
・いじめを発見した場合、特定の教職員で抱え込まず、速やかに報告・連絡・相談を行うとともに、管理職の指示の下、組織的に対応する。
・いじめられた児童およびいじめを知らせてきた児童の安全の確保を行うとともに、教育的配慮の下、いじめた児童への指導を徹底する。
・関係諸機関との連携を図り、組織的対応に努める。
エ 重大事態への対処
・いじめられた児童の心のケアに努めるとともに、落ち着いて教育を受けられる環境を確保する。
・重大事態発生について区教育委員会に報告するとともに、「HEARTS」や警察等の関係諸機関との相談・連携の下で迅速な対応を心がける。
・事実関係を把握するための調査を組織的に行い、区教育委員会による調査に協力する。
更新日:2024年04月11日 10:44:34